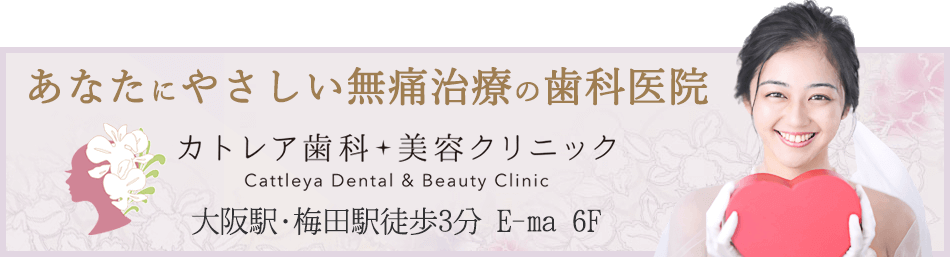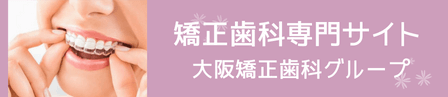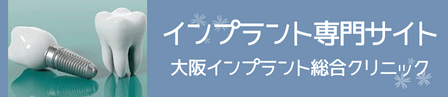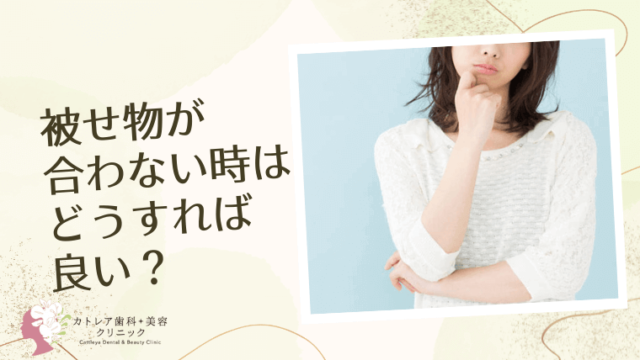被せ物と歯の間をフロスが通らない理由は?

被せ物と歯の間をフロスが通らないということはありませんか。被せ物との歯間にフロスが通らない原因などを含めてご紹介します。
フロスが通らない理由
では、デンタルフロスが、歯と歯の間を通らない理由を挙げてみましょう。大きく4つの種類に分類されます。
1. 歯間が虫歯になっている
健康な歯は舌で触れるとつるつるしていて、フロスはスッと通ります。歯の表面がデコボコしたりザラザラしている場合は、虫歯になっていることが考えられます。隣接する歯のエナメル質にざらつきがあり、フロスが引っ掛かりやすくなっている場合は、虫歯になっていないかチェックしてもらいましょう。
2. 詰め物・被せ物が合っていない
- 詰め物や被せ物の処置を終えてから長い時間が経っている
- 歯の被せ物をきちんと装着できない
いずれのケースでも、詰め物や被せ物と歯に段差があり、歯間ブラシやデンタルフロスが通りません。がたつきが見られたり、セメントの劣化により、被せ物と歯の間に隙間が出来て、虫歯のリスクを高めてしまいます。
3. 歯間に歯石が溜まり、付着している
食後歯磨きをしない状態でいると汚れが残り、歯垢が作られます。歯垢は細菌のかたまりであり、ねばねばした状態です。歯垢をきちんと除去せずに、ねばねばした状態を放置していると、歯石になり沈着します。歯と歯茎の間や、歯周ポケットに沈着した歯石は、歯ブラシやタフトブラシ、デンタルフロスで取り除くことができません。
4. 歯並びが悪い
歯並びが悪く、歯が重なっている場合は、その部分にフロスが入りにくい状態になります。歯が重なっている部分は清掃がしにくいため、汚れがついたままになりやすく、虫歯や歯周病になるリスクが高まります。気になる場合は、矯正治療をした方が良いか、歯科医院にご相談ください。
被せ物にフロスが通らない状態を放置してはダメ
虫歯の場合は対処を早く行わなければ変色や痛みが生じ、口臭、膿などのトラブルが起きます。膿が出るケースでは、根管治療が必要になるため治療が長引きます。歯石は歯周病や虫歯の原因になります。合わない被せ物を歯医者さんに行くのが面倒だからと長く使用するより、新たな被せ物を作製してお口の中を健康に保つ方が歯の費用は安くなることが多いです。
クリーニングを定期的に受診し予防していると、結果的にご自身の歯を健康に長持ちさせることができます。前までは歯間や歯肉にフロスを通すことは可能だったのに、急に通らなくなったら、なるべく早めに歯科医院を受診しましょう。
被せ物について
被せ物が歯に合う・合わないと尋ねられてもいまいちわからないという方もおられるでしょう。
詰め物と被せ物の違い
- 小さな虫歯の場合は、詰め物(インレー)
- 大きな複数本にわたる虫歯の場合は、被せもの(クラウン)
これらは補綴(ほてつ)と呼ばれる治療で、被せ物の材料も種類があります。順番にご案内します。
保険適用内での被せ物
- 強度はあるが経年劣化を起こす銀合金
- 銀を使用しているがわかりにくい硬質レジン前装冠(前歯のみ)
保険適用外の自費診療の被せ物
- セラミックの中では噛む強度があるジルコニアセラミック
- 見た目が美しいオールセラミック
- コンピューターが作製するセラミックで料金が安いセレッククラウン
- 強度は最もあるが審美性に欠けるゴールド
保険適用内の詰め物では、銀合金・樹脂(歯科用プラスチックやレジンとも呼ぶ)、保険適用外の詰め物は、セラミックや金などの材料を使用することができます。
被せ物で治療をを行う際の治療の流れ
むし歯治療で被せ物をした際に、どのような流れで被せものの治療を行うかご説明します。
- 虫歯に感染している部分をしっかりと削る
- 歯の形を整えて型どりを行う
- 削った部分に薬剤を充填し、仮の蓋をする
- 歯科技工士が被せ物を作製する
- 仮の蓋を外し、噛み合わせの高さなどを確認しながらセメントで接着する
被せ物が合っていないと、上下の歯で噛んだら違和感が生まれます。また、一部の歯に負担がかかってしまうと、噛む力で接着が取れてしまいます。それにより被せ物の下でむし歯が再発する二次虫歯になったり、歯周病、顎関節症の原因になるケースもあります。
フロスが被せ物と歯の間を通らない理由に関するQ&A
フロスが被せ物と歯の間を通らない理由は、主に以下の3つです。
1.歯間が虫歯になっている場合、隣接する歯のエナメル質にざらつきがあり、フロスが引っ掛かりやすくなります。
2.詰め物や被せ物の処置が患者に合わない場合、詰め物や被せ物と歯の間に段差が生じ、フロスが通りません。
3.歯間に歯石が溜まっている場合もフロスが通りません。
虫歯になった歯間は表面がざらざらしており、フロスが引っかかりやすくなります。虫歯菌が酸を排出し、エナメル質が溶けることで隣接する歯の表面がざらつきます。そのため、フロスが歯間に引っかかり通らない状態になります。
被せ物と歯の間にフロスが通らない状態を放置すると、虫歯のリスクが高まります。詰め物や被せ物が合っていない場合、噛む力で接着が取れてしまったり、隙間ができたりすることがあります。これにより、二次虫歯や歯周病、顎関節症の原因となる可能性があります。
まとめ

被せ物がなくても、隣接する歯と歯の間は清掃がしづらいものです。特に、補綴物がある歯間は更に掃除がしづらくなりますが、無理やり力で通してしまおうとしないでください。歯茎を痛めてしまうと、痛い部分に細菌が入り炎症を起こす可能性があります。ワックス付きのフロスなどを使用し、それでも被せ物の横にフロスが通らない場合は、歯科の診療を受け、相談することをおすすめします。